CHAPTER 2
- 次世代商社の3つの人材要件 -
PART
12
リーダー
【この章で学ぶこと】
・「リーダー」とは何かを理解する。
・「周囲を巻きこむ」にはどうしたらよいかを学ぶ。
リーダーとは?
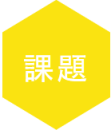
上記に対し全員が、①主将は「リーダー」であると答えるはずです。中には②副将や③セクションリーダーも「リーダー」に含める人もいると思いますが、④主務・マネージャーや⑤学生コーチは「裏方」と捉え、⑥選手は「その他大勢」と捉える人がほとんどだと思います。
「リーダーはどうあるべきか」「リーダーシップとは何か」というテーマは、過去から長きにわたり議論されてきましたが、最終的な答えはまだ見つかっていませんし、永遠に見つからないのではないでしょうか。
これまでの考え方は、「リーダーシップ」とは、生まれ持った統率者として資質のことを指し、組織の中でもっとも「リーダーシップ」を備えた選ばれし者が「リーダー」となるのが一般的でした(組織の中で一番、能力やスキルが高い人が「リーダー」となるケースもあります)。「リーダーシップ」を先天的な資質とする考え方です。一人の「リーダー」とその他大勢の「フォロワー」という位置付けになる訳です。この考え方はみなさんに馴染みのあるものではないでしょうか。「カリスマリーダー」という言葉が生まれたのも、このような背景からだと思います。
最近は、「リーダーシップ」は、誰でも後天的に身につけることができ、誰でも「リーダー」になりうるという考え方が主流になってきています。ここでもこの考え方に基づきます。
繰り返しになりますが、商社パーソンの目指すところは「イノベーティブ・グローバル・リーダー」であり、「リーダー」は「周囲を巻き込み課題を解決すること」が求められます。つまり商社パーソンは、役職に就いている/いないにかかわらず、
全員が「リーダー」
ということになります。それは、一人が「リーダー」でその他は「フォロワー」という組織よりも、全員が「リーダー」として主体的に周囲を巻き込みながら仕事をする組織の方が、組織全体のパフォーマンス(すなわち、解決できる課題の量と質)は高くなると考えるからです。今の時代、変化のスピードは極めて早く、物事がより複雑になっています。一人の「リーダー」が全てをリードしていくのには限界があります。「仲間と一緒に」という姿勢が大事であり、上司・同僚・部下やスタッフ部署の専門家、顧客など、志や目標を共にする仲間を巻き込んだ方が、より多くの知識やスキルが活用でき、より多くの優れたアイデアが浮かびます。どの役職・どのポジションにいたとしても、「リーダー」として周囲を巻き込み課題を解決することは可能です。一方、組織のトップが必ずしも「リーダー」の役割が果たせるとは限りません。要は本人が「リーダー」としての役割を果たす意思があり、スキルがあるかということになります。
そう考えると新入社員でも「リーダー」としての役割を果たすことができます。新入社員は経験や知識が乏しいのは当然のことですが、「リーダー」は一定の経験や知識がなければなれないというものでもありません。新入社員が解決できる課題のレベルはそう高くはありませんが、それでも業務プロセスの効率化といったような課題を、周囲を巻き込みながら少しでも解決することは可能であるはずです。また、会議においても新入社員だからといって黙っていてはいけません。新入社員ならではの視点というものもありますので、会議でも積極的に発言することが望まれます。
「No .2タイプ」「参謀タイプ」と自ら言う人がいます。商社では全員が「リーダー」であることが求められますので、私見としては、このようなタイプは商社には向いていないように思います。自ら「No .2タイプ」「参謀タイプ」と言う人は、「リーダー」の指示に忠実に従い行動しようとする意識が潜在的にあるように感じます。また、このタイプは評論家になりがちで、言いたいことだけ言って自らは行動に移さない人が多いと思われます。
みなさんは体育会・サークル・ゼミ・アルバイトなど何らかの組織に属していると思います。その組織の中で、主将や代表といったポジションに就いている人は、おのずと周囲から「リーダー」としての役割が期待されます。その分、本人も「リーダー」としての役割を果たそうとするでしょうし、実際にそのような機会や場面は多いと思います。自ら積極的にリーダーポジションを取りにいくと良いと思います。
一方、そのようなポジションに就いていない人でも、「リーダー」として成長するチャンスはもちろんあります。ただ、周囲から特に「リーダー」としての行動を期待されないため、自らの意思で行動を起こすことが求められます。
主将や副将といったポジションに就くことが大事なのではなく、どんな立場にいても組織の中で「リーダー」として、「周囲を巻き込みながら課題を解決」しようとする「意思」と「行動」が大切です。また、「リーダー」として、他の組織メンバーのマインドが「Fixed Mindset」であるのであれば、それを「Growth Mindset」に変え、組織全体のパフォーマンスを高めていくことも求められます。
「周囲を巻き込む」とは?
「リーダー」とは「周囲を巻き込み課題を解決する人」と定義しました。では、「周囲を巻き込む」にはどうしたらよいでしょうか?
コミュニケーション力:
一つ目は「コミュニケーション力」を高めるということです。
「コミュニケーション」と言うと、自分の考えを相手に言葉で伝えることと考えがちですが、もっと広義にとらえ「相手を理解し・相手に理解してもらう」ことであると定義します。つまり「コミュニケーション」とは「相互理解」のことだと考えるのです。
まず「相手に理解してもらう」について説明すると、「論理的」に物事を考え、相手に伝えることがもっとも重要であると考えます(「論理的思考」については、第14章で具体的に説明します)。それ以外には「身振り手振り」「表情」「声」といった「非言語」についても重要です。
一方、「相手を理解する」については、「相手に理解してもらう」以上に難しいことでしょう。人は自分中心に物事を考えがちです。意識して相手の話に耳を傾け(傾聴)、相手の意見や質問の意図を正しく理解することが求められます(第15章でも説明します)。また、「相手を理解する」ためには、第16章で説明する「多様性」を磨くことも重要です。相手に対し先入観を持たず、相手を受け入れていくことが大事になってきます。
リーダーとしての実践:
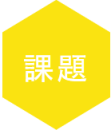
① Vision Leadership・ビジョン型リーダーシップ
(共鳴の起こし方)共有の夢に向かって人々を動かす
(風土へのインパクト)最も前向き
(適用すべき状況)変革のための新ビジョンが必要なとき、または明確な方向性が必要なとき
② Coaching Leadership・コーチ型リーダーシップ
(共鳴の起こし方)個々人の希望を組織の目標に結びつける
(風土へのインパクト)非常に前向き
(適用すべき状況)従業員の長期的才能を伸ばし、パフォーマンス向上を援助するとき
③ Democratic Leadership・関係重視型リーダーシップ
(共鳴の起こし方)人々を互いに結びつけてハーモニーを作る
(風土へのインパクト)前向き
(適用すべき状況)亀裂を修復するとき、ストレスのかかる状況下でモチベーションを高めるとき、結束を強めるとき
④Affiliative Leadership・民主型リーダーシップ
(共鳴の起こし方)提案を歓迎し、参加を通じてコミットメントを得る
(風土へのインパクト)前向き
(適用すべき状況)賛同やコンセンサスを形成するとき、または従業員から貴重な提案を得たいとき
⑤ Pacesetting Leadership・ペースセッター型リーダーシップ
(共鳴の起こし方)難度が高くやりがいのある目標の達成を目指す
(風土へのインパクト)使い方が稚拙なケースが多いため、非常にマイナスの場合が多い
(適用すべき状況)モチベーションも能力も高いチームから高レベルの結果を引き出したいとき
⑥ Commanding Leadership・強制型リーダーシップ
(共鳴の起こし方)緊急時に明確な方向性を示すことによって恐怖を鎮める
(風土へのインパクト)使い方を誤るケースが多いため、非常にマイナス
(適用すべき状況)危機的状況下、または再建始動時、または問題のある従業員に対して
どのリーダーシップスタイルが正解というわけではありません。この状況、このメンバーであれば、このリーダーシップスタイルが最も効果があると判断し、スタイルを使い分けることが大切です。また、自分の苦手なリーダーシップスタイルがあっても、他のメンバーがそのスタイルを発揮できるのであれば、その人に任せてしまえば良いのです。大事なのは、リーダーシップにはその時々に適したスタイルがあり、自分のリーダーシップスタイルの強みと弱みを客観的に認識しておくということです。日本人のリーダーは⑤と⑥が多いようです。欧米のリーダーは4つぐらいのスタイルを使い分けているという調査結果があるようです。
人々の価値観が多様化し、世の中の変化のスピードが加速している現在において、「オーセンティック・リーダーシップ」というリーダーシップスタイルが注目されています。「オーセンティック・リーダーシップ」とは、「自分らしさ」を自覚し、その「自分らしさ」を軸にして、人間関係を長期的に築き、知識だけでなく感情の面から人々を引っ張っていくというスタイルです。高い自己認識力(セルフ・アウェアネス)を通じて、自分自身の中に根源的にある「自分らしさ」を認識し、それを周囲にさらけ出すことが求められます。
もう一つの「周囲を巻き込むために必要なこと」は、ギブ・アンド・テイクに関することです。『GIVE & TAKE-「与える人」こそ成功する時代』(アダム・グラント著)によると、ギブ・アンド・テイクの関係者には「テイカー」「ギバー」「マッチャー」の3種類あります。「テイカー」は常に、与えるより多くを受け取ろうとし、自分の利益を優先する人のこと。「ギバー」はギブ・アンド・テイクの関係を相手の利益になるようにもっていき、受け取る以上に与えようとする人のこと。「マッチャー」は与えることと受け取ることのバランスを取ろうとする人のこと。「成功から最も遠い」のも「一番成功している」のもギバーですが、成功しているギバーは、自分だけでなくグループ全員が得をするように、パイ(総額)を大きくしつつ、受け取るより多くを与えても、決して自分の利益は見失わず、与えることを「計画的」に行っているといいます。成功しているギバーは、周囲に良い影響を与え、良質な人脈を形成することにより、長期的に利益を得るということです。
この章の最後になりますが、「リーダー」として「周囲を巻き込み課題を解決する」ことが求められる中で、ベースとなるのは「信頼」です。「信頼」がなければ、周囲を巻き込むことは不可能です。人から「信頼」を得るには、日々の言動の積み重ねが大事です。第17章で詳しく説明しますが、学生時代から「信頼」される人間を目指してください。
【まとめ】
・商社では全員が「リーダー」になり、「周囲を巻き込み課題を解決する」ことが求められる。
・「リーダー」となるには、意識して自ら「リーダー」としての役割を果たすよう努める。
・将来「リーダー」となるには、大学時代に「信頼」を磨く必要がある。
